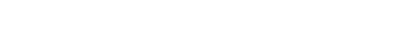相隣関係(民法)の改正(2)
2025.08.20 > 新着情報
前回に続きまして、所有者不明土地問題等の解決に向けた民法の相隣関係の改正について説明いたします。今回は、電気、ガス、水道等の各種ライフラインのための隣地使用権についてです。
従前、電気の引込線、ガス管、水道管、電話線といったライフライン設備の引込工事を行うための隣地使用については条文が存在せず、隣地の所有者がこれらを引込むための工事に同意しないときは、民法の解釈により、引込工事をすることの承諾を求める訴訟を提起し、判決に基づいて工事を行うという運用がなされてきました。
そこで、電気、ガス、水道水の供給、その他これらに類する継続的給付を受けることができない土地の所有者は、必要な範囲で、他の土地に設備を設置する権利、あるいは他人の所有する設備を使用する権利を有することが認められました。ただし、設備の設置、使用の場所、方法は、損害が最も少ないものとする必要があります。
このような設備を設置する権利や使用する権利がある場合でも、これを拒否された場合は、裁判所に対し訴訟を提起し、判決に基づいて権利の実現を図ることとなります。
他の土地等の所有者等の権利保護のために、他の土地に設備を設置し、又は他人が所有する設備を使用する者は、あらかじめ、その目的、場所及び方法を他の土地等の所有者及び他の土地を現に使用している者に通知しなければならないとされました。なお、隣地使用権の場合と異なり、事後通知が認められていませんので、隣地使用者が所在不明等の場合には公示による意思表示(民法98条)により通知を行う必要があります。
なお、隣人が存在する場合、工事のために一時的に隣地を使用する場合、実損害を償金として支払う必要があります。また、設備の設置により土地が継続的に使用できなくなる場合は、設備設置部分の使用料相当分を支払う必要があります。たとえば、水道管を地上に設置し、その部分の土地の使用ができなくなる場合です。
新着情報INFORMATION
法律Q&AQ&A
アクセスACCESS
〒540-6591
大阪市中央区大手前1-7-31 OMMビル21F
TEL.06-6945-0308 FAX.06-6945-0691