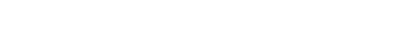相隣関係(民法)の改正(3)
2025.09.03 > 新着情報
前回・前々回と、所有者不明土地問題等の解決に向けた民法の相隣関係の改正について説明いたしました。今回は、越境した枝の切除についてです。
従前、隣地から越境した竹木の根は、土地所有者が切り取ることができるとされていました。この点は民法改正後も変わりはありません。
しかし、越境した竹木の枝については、これを切り取ることは認められていませんでした。そこで、この切除のためには訴訟を提起し、越境についての所有者に枝の切除を求める判断を得て、執行手続により実現を図らなければなりませんでした。
そこで、今回の民法改正は、⓵竹木の所有者に越境した枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内(2週間程度)に切除しないとき、⓶竹木の所有者を知ることができず、あるいはその所在を知ることができないとき、または⓷急迫の事情があるときのいずれかの要件を満たした場合には、越境した枝を自ら切ることができるとされました。
なお、竹木が共有地の場合、従前は原則として共有者全員の同意を得なければ枝を切除できないとされていました。しかし、今回の改正により、⓵の催告に関しては、枝が共有の場合、基本的に共有者全員に催告をする必要がありますが、一部の共有者が所在不明等のときは、その者との関係では上記⓶に該当し、催告は不要となります。
また、改正民法では、越境した枝にかかる竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができることとされました(改正民法233条2項)。この規定により、越境された側の土地の所有者は、竹木の共有者一人に枝の切除を求めることができます。また、竹木の共有者の一人から承諾を得れば、越境された側の土地の所有者などの他人がその共有者に代わって枝を切り取ることができると考えられます。
改正民法により、今後は越境した枝の所有者が所在不明の場合や相続により遺産共有となっている場合にも円滑に枝の切除を行いやすくなります。
新着情報INFORMATION
法律Q&AQ&A
アクセスACCESS
〒540-6591
大阪市中央区大手前1-7-31 OMMビル21F
TEL.06-6945-0308 FAX.06-6945-0691